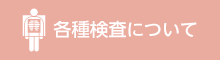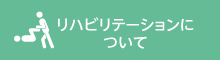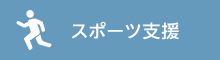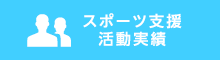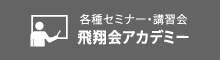スポーツドクターコラム
ひろスポ版【第2回】~10代成長期のサッカー、バスケ選手などにに多い「有痛性外脛骨障害」の原因と対策~
2014/05/20
有痛性外脛骨障害
2026/01/13 情報更新前回の腰椎分離症に続いて、今回もスポーツ活動の盛んな10歳から15歳の思春期に発症することが多い足部の障害についてお話しましょう。前回同様、ポイントになる表現、名称などには「 」をつけました。 今回は「有痛性外脛骨障害」(ゆうつうせい・がいけいこつしょうがい)というあまり聞きなれないスポーツ障害についてです。名称は知られていなくても、よく見られる症例ですから注意が必要です。足の「内くるぶし」の前方足底側に「硬い突起物」が触れられるようになり、そこを押さえると強い痛みがあります。 多くの場合は運動を繰り返しているうちに徐々に痛みが強くなります。捻挫などの外傷がきっかけになることもあります。
小・中・高校生に多い足底の痛みの原因は「正常な骨」とは“別”の「過剰骨」
では、どんな病態(なぜ痛みを生じるか?)なのでしょうか? 足の骨の中に舟状骨(しゅうじょうこつ)と呼ばれる部位があります。(イラスト参照)。舟状骨には「後脛骨筋腱」(こうけいこつきんけん)、いわゆる「筋(すじ)」が付着しています。付着している位置は、内足の後方。要するに、先ほどお話しました「内くるぶし」先方の足底部にあたるところです。ここに「過剰骨」(かじょうこつ)が見られるようになると痛みを発症します。

「過剰骨」というのは正常な骨の横に、もうひとつ別の骨ができることを言います。 この「過剰骨」は、どういう過程でできてくるのでしょうか? 赤ちゃんの骨はほとんど軟骨です。そしていくつかの骨端核(こったんかく)と呼ばれる小さな骨を軟骨が囲んでいる構造になっています。軟骨は骨端核の成長とともにだんだん骨に変化していきます。骨端核同士がくっついてそれがやがて3つになり、2つになり、という具合です。 10~15歳の一番成長する時期に、「軟骨がなくなって」ひとつになるべき骨が、「軟骨が残ったまま」でくっつくケースが見受けられます。こうなると非常に弱い結合になります。大人の骨になる際に「ひとつになるべき骨」が「軟骨によってくっついている状態」です。 そういう時に過剰なストレスが加わると、「後脛骨筋腱(すじ)」が舟状骨に付着する内足後方に、「外脛骨」(がいけいこつ)と呼ばれる「過剰骨」が見られるようになります。 要するに成長の過程で「ひとつになるべき」舟状骨が軟骨で結合してしまいます。この場合、見た目は「ふたつに分かれてしまっている」状態になります。 ただ「分かれた状態になる人」と「そうならない人」がいます。実は正常な人でも15パーセント前後に「外脛骨」が見られます。また女性の方に多く、その80~90パーセントという高い確率で両足ともに発症します。
足底へのストレスが蓄積されやすいスポーツ競技者は要注意
この「外脛骨」に「後脛骨筋腱(すじ)」の引っ張る力、「牽引力」が働くと痛みが生じます。足へのストレスが痛みの原因になります。 ストレスは走ったり、跳んだりという動きの繰り返しによって蓄積されます。足底には「アーチ」があってそこには「足底腱膜」という「筋(すじ)」があります。足の骨が「弓」の役目を、「筋(すじ)」が「弦」の役目をしている、と考えて下さい。この「弓」と「弦」が相互に働いて足の形状を保っています。足の裏が下に落っこちようとすると「弦」が引っ張り、「弓」の力が働くことにより足底の「アーチ」が作られます。 当然のことながら弓道、アーチェリーなど「走」「跳」といった動きのない競技では「外脛骨」が生じることは少ないようです。逆に走ったり、ジャンプしたり、と言えば新体操、バレエダンサー(バレリーナ)の動きなどがまさにそうです。こうした競技では足へのストレスが大きく、またサッカー、バスケットボールなど足を内転させる動きが多い場合にも足へのストレスが蓄積されていきます。
治療法は「安静」「運動制限」「足底板の使用」など
治療については、基本的には手術(外脛骨除去)をしない「保存的治療」で十分です。痛みなどの症状を繰り返すことも多いのですが、骨の成長が自然に停止するころには治ります。 「保存的治療」としては「運動の制限」やギプスなどの「外固定」を併用した「安静」が行われます。外脛骨部への刺激を軽減する目的で足の底に靴の中敷きのような感じで「足底板(インソール)」を用いる方法もあります。症状が継続する際に「ステロイド剤の局所注射」を行う方法もありますが、これは成長を止めることにも繋がりますのでお勧めできません。 「再発防止」のためには「後脛骨筋」のストレッチやスポーツのあとのアイシングが有効です。また、自分の足にフィットしたシューズを履くようにしてください。「足底板」を使用するのもいいでしょう。 スポーツ選手はもちろんですが、日頃あまり体を動かさない方でも足、特に足底は立つ、歩く、階段を上がるなどの動作に対して大切な役割を担っています。みなさんも日頃からご自分の足底の状態をチェックする習慣を身に着け、健康な毎日を送っていただきたいと思います。 スポーツドクターコラムは整形外科医師 寛田クリニック院長 寛田 司がスポーツ医療、スポーツ障害の症状、治療について分りやすく解説します。
有痛性外脛骨障害 Q&A
Q1. 子どもが「内くるぶしの下あたりが痛い」と訴えています。どう判断すればいいでしょうか?
A. 成長期に足の内側に「硬い出っ張り」が触れる場合や、運動後にその部位を押すと強い痛みを訴える場合は、有痛性外脛骨障害の可能性があります。整形外科で X線撮影 などにより確認が可能です。
Q2. 有痛性外脛骨障害は自然に治るのでしょうか?
A. 多くの場合、成長が終わるころには症状が軽快します。成長期の一過性の障害であり、適切な安静や運動制限を行うことで手術に至るケースはまれです。
Q3. どんな運動を制限すべきですか?
A. サッカーやバスケットボールなど走る・跳ぶ・急な方向転換を繰り返す競技では、足の内側に大きな負担がかかります。痛みが強い時期には次の工夫が有効です。
- 試合や長時間の練習は休む
- ダッシュ・ジャンプ中心のメニューを減らす
- ウォーキングや水泳など、足底への負担が少ない運動に切り替える
- 練習後は必ずアイシングを行い、後脛骨筋のストレッチを実施
- 指導者・コーチに有痛性外脛骨障害であることを伝え、練習メニューの調整を依頼
完全に競技をやめる必要はありません。痛みの程度に応じて調整し、周囲と連携して足への負担を軽減しましょう。
Q4. 親として日常生活で注意できることはありますか?
A. 足に合ったシューズを選び、運動後のストレッチやアイシングを習慣化しましょう。特に足底板(インソール)の使用は再発予防に役立ちます。
インソールの主な効果:
- アーチのサポート:土踏まずを支え、舟状骨や外脛骨への負担を軽減
- 衝撃吸収:走跳動作の衝撃を和らげる
- 動きの安定化:過度な内反を防ぎ、後脛骨筋へのストレスを軽減
市販のスポーツ用でも一定の効果はありますが、症状が強い場合はオーダーメイドインソールを推奨します(医師の診断書に基づき保険適用となる場合あり)。自己判断せず、まずはかかりつけ医に相談を。
Q5. 手術が必要になる場合はどのような特徴でしょうか?
A. 成長期では多くが保存的治療で改善しますが、次のような場合には外脛骨切除術が検討されます。
- 安静やインソールでも長期間改善しない
- 強い痛みで日常生活に支障がある
- 外脛骨が大きく突出し、靴に当たって炎症・腫れを反復
- 成長が終了しても改善しない
術式の概要:突出した外脛骨を切除し、必要に応じて後脛骨筋腱を舟状骨に縫着して安定化します。
一般的な経過の目安:
- 固定(ギプス/シーネ):約2〜4週間
- リハビリ開始:固定除去後すぐ(歩行訓練・筋力回復)
- 競技復帰:全体でおおよそ2〜3か月
個人差・競技特性で前後します。早期復帰の焦りは再発リスクになるため、復帰時期は必ず主治医と相談してください。

飛翔会の整形外科クリニック