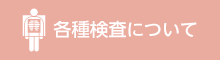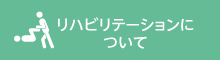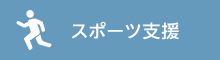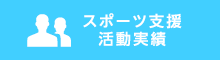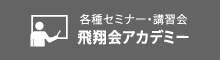スポーツドクターコラム
骨粗しょう症治療薬は本当に“自分に合った”ものですか?
2025/08/06
骨がもろくなっているから薬を出します――そう言われて処方された薬、あなたはそれが本当に自分に合ったものだと思っていますか?
骨粗しょう症の治療薬には、実はさまざまな種類があります。半年に1回の注射で済むもの、毎日飲むタイプ、骨が壊れるのを防ぐ薬、逆に骨を作る力を高める薬もあります。どれを選ぶかで、効果も副作用も、そして続けやすさも大きく変わってきます。
たとえば、プラリアという注射薬は半年に1回の皮下注射で済み、背骨も足のつけ根も含めて幅広い骨折を防いでくれる、非常に効果の高い薬です。ただしこの薬には一つ落とし穴があります。中止した後、急激に骨密度が下がり、椎体骨折のリスクが一気に高まるケースがあるのです。つまり、一度始めたら続ける前提で使う薬なのです。
一方、ボンビバという薬は月に1回の飲み薬や注射薬で、プラリアほど強力ではないかもしれませんが、継続のしやすさや費用面で選ばれることがよくあります。背骨の骨折には効果がありますが、大腿骨など他の部位ではエビデンスがやや弱めです。
フォルテオという薬もあります。これは自己注射を毎日行う必要がありますが、骨を新しく作る作用があり、骨密度が非常に低い方や、すでに複数回の骨折歴があるような重症のケースには適しています。注射と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、実際はペン型のデバイスで比較的簡単に使えますし、副作用も少ないとされています。
どれも一長一短。だからこそ、自分の体の状態をよく知ることが重要になります。 ここで参考になるのが、薬ごとの効果を比較した表です。
| 分類 | 一般名(商品名) | 骨密度 | 椎体骨折 | 非椎体骨折 | 大腿骨近位部骨折 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP系 | アレンドロン酸(フォサマック等) | A | A | A | A |
| BP系 | リセドロン酸(アクトネル等) | A | A | A | A |
| BP系 | イバンドロン酸(ボンビバ) | A | A | B | C |
| 抗RANKL抗体 | デノスマブ(プラリア) | A | A | A | A |
| 骨形成促進薬 | テリパラチド(フォルテオ) | A | A | A | C |
| 骨形成+吸収抑制 | ロモソズマブ(イベニティ) | A | A | B | B |
この表にある「A」「B」「C」は、それぞれの薬がどれだけ効果を示すかのエビデンス評価です。Aは信頼性が高く効果も十分にあるという意味で、Bはやや限定的、Cは現時点での効果が不明瞭または乏しいという評価です。(※各薬剤の個別解説は既述の通り)
骨粗しょう症治療薬は、全体として非常に効果が高い一方で、いくつかの共通する副作用リスクがあることも事実です。 特に、ビスホスホネート製剤(アレンドロン酸、リセドロン酸、イバンドロン酸)やデノスマブ(プラリア)では、まれに「顎骨壊死」や「非定型大腿骨骨折」が起きる可能性があり、長期使用時には注意が必要です。また、プラリアやフォルテオでは「低カルシウム血症」のリスクもあり、定期的な血液検査が求められます。ロモソズマブ(イベニティ)においては心血管イベント(心筋梗塞や脳卒中)のリスクが指摘されており、既往歴のある方は特に慎重な判断が求められます。
しかしこれらの副作用はどれも「まれ」なものであり、適切なモニタリングや予防策を講じれば、安全に使用できる薬がほとんどです。より安全性を重視したい方は、「骨粗鬆症マネージャー」が在籍する医療機関での治療を検討するのも一つの方法です。骨粗鬆症マネージャーとは、日本骨粗鬆症学会が定めた専門的な教育プログラムを修了し、認定試験に合格した専門資格者です。治療選択や生活指導において、より専門的かつ個別性の高い対応が期待できます。
つまり、「薬が怖いから使わない」ではなく、「自分に合った薬を、正しい方法で使う」ことが骨折予防の鍵なのです。
こうした薬の選び方を考えるときに大切なのが、「今の自分の骨の状態をちゃんと知っておくこと」です。骨密度検査はそのための重要な指標になります。
腰椎や大腿骨の骨密度を測るDXA(デキサ)法は、骨粗しょう症の診断と薬剤選択において標準とされている方法です。すでに圧迫骨折などがある場合には、DXAを行わなくても診断がつくこともありますが、治療効果を客観的に把握するにはやはり骨密度のデータが役立ちます。
最近では全国の自治体で骨密度検診への公費補助制度が広がりつつあります。広島市では、20歳以上の女性、40歳以上の男性を対象に、DXA法による骨密度検査を1,000円前後で受けられる制度があります。一定の条件を満たせば、無料になることもあります。お住まいの地域によって制度は異なりますが、まずは市町村の保健センターや広報を確認してみるとよいでしょう。検査は骨折を防ぐ第一歩。数値を知ることが、薬を「選ぶ」のではなく「納得して選ぶ」ための大切な鍵になります。

飛翔会の整形外科クリニック