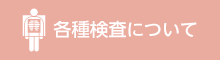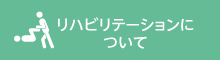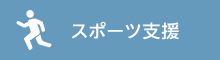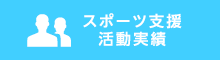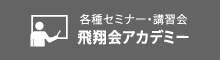スポーツドクターコラム
No.61「肋骨骨折の主な原因は外傷性か疲労骨折」
2008/09/10
肋骨骨折は、スポーツ選手によくみられる胸部の障害の1つです。主な発生原因としては、転倒や打撲などによる外傷性のものと、骨の同一部位に繰り返し小さなストレスが加わって起こる疲労骨折の2つがあります。 【2025年注訳:現在では、画像診断の進歩によりCTやMRIによる微小骨折線の検出が容易になり、軽度の疲労骨折でも早期診断が可能となっています。特にMRIでは骨髄浮腫の評価が重要で、X線で異常がなくても診断が確定できるケースが増えています。】 外傷性のタイプは、コンタクトスポーツで多々起こります。接触プレーなどによって胸部を強打し、骨折してしまうのです。例えばサッカーで競り合ったときや、野球のクロスプレーなどで負傷することもあるでしょう。 疲労骨折のタイプは、肋骨と肋骨の間を広げたり縮めたりする動作を何度も繰り返すことによって生じます。ゴルフの初心者によくみられ、利き手の反対側の第2肋骨~第9肋骨に発生することが多いようです。スポーツ活動に必要な基礎体力の欠如やスイングの基本動作の未熟、集中的な過度の打球練習などが疲労骨折の要因とされています。コースプレー中よりも、練習場で短時間に集中して練習したときの方が起きやすいのも特徴です。 また、野球もゴルフ同様に肋骨の疲労骨折が多いスポーツと言えます。打者の場合は、バットスイングの繰り返しが主な原因です。特に技術面で発展途上の高校生などが、引っ張ったり流しに行くスイングを無理に習得しようとすると、肋骨に負荷がかかり痛めてしまいます。 【2025年注訳:高校・大学野球では、肋骨疲労骨折のうち約7割が打者で発生すると報告されています。最近では、バットの材質やスイング速度向上に伴うトルク負荷増加も関係しており、指導現場では筋力バランス評価の導入が推奨されています。近年では、スイング時の体幹回旋筋群(特に腹斜筋群)の不均衡が大きく関与していることが分かってきました。腹斜筋や広背筋の過剰収縮が肋骨に捻転応力を加えるため、フォームの左右差や柔軟性の不足もリスク因子とされています。】 一方、投手の場合は、鎖骨の上にある第1肋骨を負傷してしまうケースが過去にも複数ありました。投球が手投げになっていたり、足を踏み出すポイントが一定していない選手は、注意しなければなりません。首と肩の間を何度も広げたり縮めたりする動きによって、負荷のかかりやすい投球フォームになってしまっています。発生部位が肩に近いため、肩を痛めたと勘違いしやすいのですが、肩関節には問題がなく、首を捻ると痛い場合は、この障害を疑うことができるでしょう。 【2025年注訳:第1肋骨の疲労骨折は、鎖骨下動静脈や腕神経叢の圧迫を伴う「胸郭出口症候群(TOS)」と誤診されることもあり、MRI・CTでの部位特定が重要です。また、フォーム修正だけでなく、肩甲骨の可動性改善も再発予防の鍵となります。】 診察では、患部だけでなく投球フォームをチェックすることも大切です。体幹のバランスが悪い状態で無理をして投げると故障しやすく、やはり下半身がしっかりしていなければ投球動作は安定しません。故障してしまったときは、治療とともに障害の原因となっている投球動作の改善、体幹の強化にもしっかり取り組みましょう。 【2025年注訳:体幹トレーニングでは、腹斜筋・脊柱起立筋だけでなく、深部安定筋群(いわゆるインナーユニット)の連動性が重要視されるようになっています。リハビリ期には、呼吸トレーニングと胸郭可動性の再獲得を同時に行うプログラムが有効です。】 治療は、痛みを引き起こしている動作を止めて安静にすることが第一です。比較的、予後は良好な障害で、手術をしなくてもほとんどの場合で自然に治癒します。およそ1ヵ月程度で、症状は落ち着いてくるでしょう。ただ安静にすると言っても、下半身の筋力トレーニングを行うことは可能です。第1肋骨を負傷した場合であれば、ランニングまでできることもあります。患部に負荷がかからない範囲で、体力が落ちないように努めましょう。痛みが軽減していれば超音波骨折治療器(LIPUS)を併用することで治癒促進が期待できるとされます。また、早期復帰を目指す場合には、低負荷有酸素運動や体幹安定化エクササイズを並行して行うリハビリプランが一般的です。肋骨骨折の臨床では、画像評価・フォーム解析・体幹筋バランス評価の三本柱で総合的にアプローチすることが標準的になっています。再発予防には、スポーツ種目ごとの特異的動作(スイング、投球、体幹回旋)の解析が欠かせません。
肋骨骨折(外傷性・疲労骨折)に関するFAQ
Q1. 肋骨骨折の原因にはどんなタイプがありますか?
A. 大きく分けて「外傷性」と「疲労骨折」の2つがあります。外傷性は転倒や打撲など強い衝撃で起こり、コンタクトスポーツに多く見られます。一方、疲労骨折は繰り返されるスイングや回旋動作など、軽い力の積み重ねによって発生します。ゴルフや野球など、胸郭をねじる動作を多用する競技に多く見られます。
Q2. 疲労骨折はどんな人に起きやすいですか?
A. 初心者や、練習量が急に増えた選手、体幹や肩回りの柔軟性が不足している人に起きやすいです。とくに成長期の学生では、筋力と骨の発達バランスが不十分なため、胸郭に繰り返しストレスがかかりやすくなります。フォームの左右差や姿勢の乱れも発症要因になります。
Q3. 痛みの特徴にはどんなものがありますか?
A. 動いた瞬間に「ズキッ」と刺すような痛みが出るのが特徴です。咳・くしゃみ・深呼吸・笑う・寝返りなど、胸郭を動かす動作で痛みが増します。押すと局所的に強い圧痛があり、痛む位置がはっきりしている場合は肋骨骨折を疑います。
Q4. レントゲンで写らないことがあると聞きましたが本当ですか?
A. はい、初期の疲労骨折ではレントゲンに写らないことがあります。MRIでは骨の内部の変化(骨髄浮腫)を早期に検出できるため、痛みの原因をより正確に特定できます。最近では軽度例でもMRIやCTを併用することで、より早期診断が可能になっています。
Q5. 治療はどのように行いますか?
A. まずは安静を保ち、痛みを誘発する動作を控えることが基本です。ほとんどのケースは自然に治癒しますが、痛みが強い時期には胸部サポーター(肋骨バンド)を短期間だけ使用して安定させる場合もあります。超音波骨折治療器(LIPUS)を併用すると治癒促進が期待できます。症状が落ち着いたら、体幹や肩甲帯の柔軟性を回復させるリハビリを段階的に進めます。
Q6. スポーツ復帰の目安はどれくらいですか?
A. 一般的には3〜6週間程度で痛みが軽減しますが、骨癒合や競技動作の負荷によって差があります。再発を防ぐため、「痛みが消えた=完治」ではなく、回旋やスイング時に痛みがない状態を確認してから復帰することが大切です。医師や理学療法士の指示に従い、段階的に練習を再開しましょう。
Q7. 肋骨骨折と間違えやすい症状はありますか?
A. 肋間筋肉離れや肋軟骨損傷、胸郭出口症候群などと区別が必要です。痛みの出る動作や圧痛部位、画像検査の結果を組み合わせて正確に診断します。「肩や背中が痛い」と感じて受診した結果、実は肋骨骨折だったというケースも珍しくありません。
Q8. コンタクトスポーツで予防する方法はありますか?
A. 胸部を守るプロテクターの着用は有効ですが、完全には防げません。それよりも体幹・肩甲帯の柔軟性を維持し、フォームの偏りを減らすことが重要です。また、オフ期間の筋力低下を防ぎ、復帰時に急激な負荷をかけないよう調整しましょう。
Q9. 肋骨骨折のとき呼吸が浅くなるのはなぜですか?
A. 呼吸のたびに骨折部が動いて痛むため、無意識に浅い呼吸になってしまいます。これを放置すると、肺の換気量が減り、二次的に肺炎を起こすことがあります。痛み止めや姿勢調整を行いながら、医師の指導のもとで痛みを抑えて深呼吸を保つことが大切です。
Q10. 保護者が気づけるサインと、日常生活での注意点は?
A. 呼吸・咳・寝返り・笑う・体幹の反りやひねりで胸の一点が痛む、触ると局所に強い圧痛がある――こうした所見は肋骨疲労骨折のサインです。児童や学生では「笑うと胸が痛い」「咳をするとズキッとする」「深呼吸や横になると痛い」などの訴えから発覚することが多く、打撲や筋肉痛と誤解されて受診が遅れるケースもあります。数日たっても改善しない/夜間痛が強い/深呼吸ができない/打撲後に痛みが増す場合は、早めに整形外科を受診してください。日常では、重い荷物を片側で持つ・強いねじり・反り・前屈を避け、咳やくしゃみの際はタオルや手で胸を軽く押さえて痛みを減らします。寝返りは抱き枕などで体幹の揺れを抑えると楽です。痛みが強い時期のみ短期間の胸部サポーター(肋骨バンド)で安定させる方法はありますが、長期使用は筋力低下や呼吸制限の原因になるため避け、医師の指示に従ってください。早期受診により治癒計画と復帰見通しを立てやすくなります。
Q11. スポーツドクターの診察ではどんな点を重視しますか?
A. 痛みの強さや発生時期だけでなく、どの動作で痛みが出るかを重視して診察します。同じ「肋骨の痛み」でも、呼吸や体幹の回旋、投球など、痛みを誘発する動作が異なれば原因も異なるためです。また、圧痛部位と骨折線の位置を一致させることで診断の精度を高め、必要に応じてX線・MRI・CTを組み合わせて確認します。さらに、肋間筋損傷・肋軟骨炎・胸郭出口症候群(TOS)など、肋骨骨折と似た症状を示す疾患との鑑別も重要です。これらを丁寧に見分けることで、痛みの本当の原因を特定し、不要な安静や誤ったトレーニング再開を防ぐことができます。再発予防の観点からは、体幹や肩甲帯の柔軟性、筋バランス、呼吸の癖なども含めて総合的に評価します。
Q12. 再発を防ぐにはどうすればいいですか?
A. 原因動作(スイング・投球・回旋など)を解析し、体幹筋群の使い方を改善することが大切です。特に、腹斜筋・広背筋・前鋸筋などの回旋筋群の左右バランスを整えるトレーニングが有効です。また、復帰直後は練習量を段階的に戻し、睡眠不足や栄養不良による骨密度低下にも注意しましょう。
スポーツドクターコラムは整形外科医師 寛田クリニック院長 寛田 司がスポーツ医療、スポーツ障害の症状、治療について分りやすく解説します。

飛翔会の整形外科クリニック